「どうせお金を払うなら、少しでも“良い着物”を選びたいですよね?」
でも、見た目だけじゃ分からないのが、着物の難しいところ。 「なんとなく綺麗」「高そうに見える」だけで判断してしまうと、実は見えない部分で損しているかもしれません。
私は約8年間、着物の製造現場に身を置いてきました。白い反物から、華やかな着物が仕上がるまでの一連の工程に携わってきた経験があります。
この記事では、同じ価格帯の着物の中でも「より質の良い一枚」を見抜くためのヒントを、なるべく専門用語を使わず、分かりやすくお伝えしていきます👘✨
最後まで読めば、あなたも着物の“目利き”になれるかもしれませんよ。
1. 着物の重さは“縦糸の多さ”で決まる!白くても高い生地とは?
着物の生地は、縦糸(たていと)と横糸(よこいと)で織られています。 このうち、縦糸の本数が多いほど、
- 生地が厚く、しっかりとした重みを持つ
- 空気を含んで「トロッ」とした手触りになる
- 着物の形になっても崩れにくく、美しい着姿になる
という特徴があります。
実際、白い反物の時点でずっしりと重さを感じるものは、かなり贅沢に糸が使われており、それだけで“いい生地”の証拠と言えます。
🧵【例:正絹生地での違い】
- 高品質:空気を含むような柔らかさとツヤ
- 低品質:シャリっと軽く、カサカサした感触
もちろん、季節によって生地は変わります。夏は絽(ろ)や紗(しゃ)という透け感のある素材が好まれますが、今回はフォーマル着物に使われる“正絹”に絞ってお話しします。
見た目では判断しにくいからこそ、「手に持ったときの重み」は、良い着物を見抜くための第一関門なんです。

2. 柄の“描き方”に注目!手描き友禅と型友禅の違い
同じ柄に見えても、その作り方で価値がまったく変わってきます。
着物の柄は、大きく分けて以下の方法で描かれています。
✅ 手描き友禅
- 一点ずつ手で描かれている
- にじみや線のはみ出しも“味”として価値がある
- 染料が裏に抜けているのが特徴

✅ 型友禅
- 型紙を使って色をのせる方法
- 色ムラがなく、均一で美しい仕上がり
- 製造効率が高く、大量生産向き
最近では、インクジェットプリントという方法も増えています。 これも型友禅に近い分類ですが、印刷感が強く、手描きに比べると立体感や風合いが劣ります。

🎨【見分けるヒント】
- 絵柄にグラデーションやかすれがある → 手描きの可能性大
- 色が均一で整っている → 型友禅やプリントの可能性
とはいえ、どれが良い・悪いではなく、自分が「一目惚れした柄」を選ぶのが一番です。その上で「どう描かれているか」を知ることが、満足度の高い買い物につながります。
3. 着物全体に色を入れる“引き染め”の魅力
「生地の白を活かした着物」も美しいですが、着物全体に色が入っているものも、また違った魅力があります。
その代表的な技法が“引き染め”。 職人が大きな刷毛を使い、手作業で生地全体を染め上げていきます。
🖌️【注目ポイント】
- 一色染めでもムラがなく、深みのある色
- 絞りや桶染めなど、さらに手間のかかる技法も存在
- 高級品ほど均一でなめらかな染め上がり
絞りの入った“桶染め”などは、特に技術が必要で、価格も上がりますが、そのぶん芸術性が高いです。
4. 金箔が施された着物|接着剤に注目せよ
キラリと光る金箔入りの着物、華やかですよね✨
「技法には、輪転、手箔、金筒、盛り金」
でも、金箔は時間とともに剥がれてしまうことも。 その原因の多くは、実は「接着剤の質」にあります。
💡【金箔の仕組み】
- 金箔の下には、ゴムのような接着剤が塗られている
- 熱を加えて圧着することで定着する
- 安価な接着剤は粘着力が弱く、すぐ剥がれる
柄の縁に沿って、黄色・オレンジ・グレーのような色の接着剤が見えることがあります。 それが多く残っていて、金箔が剥がれかけている場合は、耐久性に不安がある証拠です。
金箔の美しさに目を奪われたら、そっと縁を見てみてください。

5. 着物を立体的に魅せる“駒刺繍”
着物の柄の一部に金糸や銀糸で刺繍が入っているものを見たことはありますか?
これを“駒刺繍”といいます。
🏵️【駒刺繍の特徴】
- 柄の中に立体感と輝きを加える
- 特に、左前身頃に施されることが多い
- フォーマルな着物ほど、刺繍が多い傾向
駒刺繍の技術は熟練の職人が手がけるもので、手間がかかる分、価格も高くなります。
「ちょっと豪華な着物を選びたい」そんな時は、この刺繍の有無が判断材料になります。
6. 見えないおしゃれ、“額縁八掛”で差がつく
最後に、“裏地”にこだわっている着物をご紹介。
着物の裾や裏に使われる“八掛(はっかけ)”という部分に、額縁のように色を入れる技法を“額縁八掛”と呼びます。
👀【額縁八掛の魅力】
- 裾まわりにアクセントが生まれる
- 着たときに内側から見える色気が粋
- 既製品よりもオーダー品に多く使われる
「見えないところまで手がかけられている」 これもまた、良い着物のひとつの条件です。
まとめ|“重さ”のある着物は、信頼の証
たくさんの見分け方をご紹介してきましたが、まずはとにかく、“生地の重さ”を感じてみてください。
・手に取った時にズシッと重みがあるか ・しなやかで空気を含んだ感触か ・安っぽく軽い、カサカサした感じではないか
これらは、写真や見た目では絶対に判断できません。 実際に触って、持って、感じることが大切です。
あなたがこれから選ぶ一枚が、長く寄り添える着物になりますように。
そして、この記事がその手助けになりますように。
📍【おさらい】良い着物を見抜くポイントまとめ
- ✅ 生地の重みと厚み(縦糸の本数)
- ✅ 手描き or 型友禅(染めの技法)
- ✅ 全体染めの丁寧さ(引き染め)
- ✅ 金箔の貼り方と剥がれの有無
- ✅ 駒刺繍の有無と位置
- ✅ 裏地まで丁寧に作られているか
👘 着物選びは「自分の感覚」を信じることも大切。 でも、その感覚に“確かな知識”が加わると、もっと強くなれるんです。
今後もこうした着物に関する“ちょっと得する目利きの話”を更新していきますので、ぜひまた覗いてくださいね。
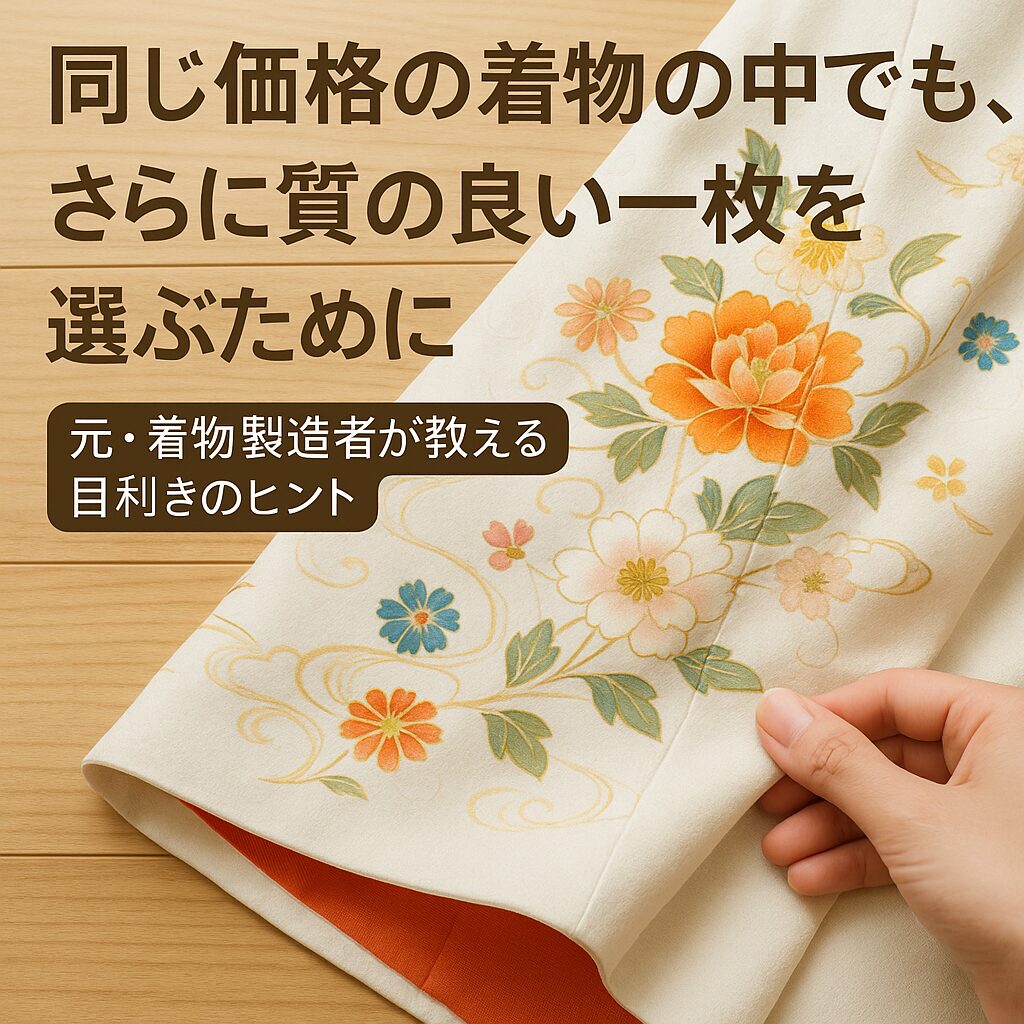


コメント